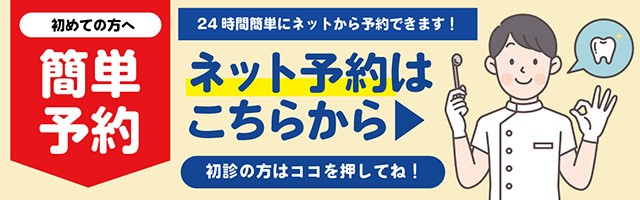緊急報告!麻酔が効きやすいとき、効きにくい時
こんばんは
京都市伏見区桃山南口の仁科歯科医院の仁科真吾です
今日は寒いですね
さっき六地蔵のラーメンを食べて帰ってきたのですが
雪が積もってました
今年は暖冬かな?そんなことをブログで書いていたのですがハズレましたね
今日は麻酔が効きやすい状態と効きにくい状態はどんな時?でなぜ?を書いていこうと思います
これは歯科薬理学で習うことなんですが
まあ歯科の学生さんもこのブログを見ているとのことなので書いていきますね
麻酔を効かしている部位がアルカリ性に傾いて入れば麻酔の成分が脂溶性になるため
結合組織などを通過しやすくなります
つまり効きやすいということなんです
しかし炎症が起きている場合
この部位は酸性に傾いているので麻酔が効きにくいのです
どれぐらいのPhなんや?
そうPh7です
これ以下なら麻酔が効きにくいしこれ以上なら効きやすいんです
一般の患者さんはへーって思ってみといてください
歯科学生の人はちゃんと化学式を覚えてください
麻酔を使う時は多く炎症が起きている時が多いのですが
例えば歯髄炎、外傷、歯周炎、歯肉炎、などなど
炎症が起きていない場合の外科というのは
んー例えば歯周病のフラッオペ、小帯切除、消炎後の抜歯、など
つまり痛みがない時の外科ですね
基本抜歯というものは腫れている時には行いません
通常、腫れている状態を抑えてからつまり消炎処置を行ってから行います
なぜか?腫れている状態で外科を行うとさらに炎症が大きくなるからです